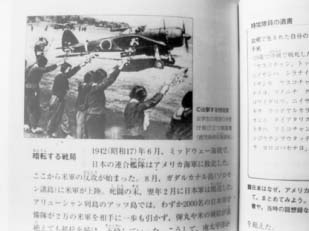2001年06月22日発行694号
【「つくる会」歴史教科書 / / 戦争協力は「国民の心得」!! / 国家への献身を説く】 | ||
「新しい歴史教科書をつくる会」による歴史教科書(扶桑社)は、「自国中心の偏った歴史観」と評価されることが多い。間違いではないが、より正確には「国家権力に都合よく、その行為を正当化する歴史観」と言うべきだろう。自国のために献身することが国民の心得だと説く――そんな「つくる会」教科書の特徴をみていこう。
国家権力に都合よく「つくる会」教科書には、ほかの教科書と大きく違う点がたくさんある。そのひとつが、およそ教科書的ではない文体である。執筆者の感情を織り交ぜた講談チックな文章が実に多いのだ。 「東郷平八郎司令官率いる日本の連合艦隊は、兵員の高い士気とたくみな戦術でバルチック艦隊を全滅させ、世界の海戦史に残る驚異的な勝利をおさめた」 「このこと(真珠湾攻撃)が報道されると、日本国民の気分は一気に高まり、長い日中戦争の陰うつな気分が一変した。第一次大戦以降、力をつけてきた日本とアメリカがついに対決することになったのである」 講談調の文体で読者(子ども)の心情を日本という国家と一体化させようとする意図は明白だろう。こんな文章が教室で音読される光景を想像すると、ぞっとする。 国家権力に都合のいい歴史観を「つくる会」教科書は押しつけようとする。このため、民衆の生活に関する記述が極端に少ない。貧困や生活苦、そして圧政に抗して立ち上がった人々の姿は、まったくと言っていいほど描かれない。 この姿勢は文化史にいたるまで徹底している。奈良時代の文化では、天皇の和歌を仰々しく紹介する一方で、当時の民衆の生活を考える題材として大抵の教科書がとりあげている山上憶良の「貧窮問答歌」は載せない。「つくる会」教科書がどのような人々の目線から歴史を語っているかが、よくわかる。 「教育勅語」を絶賛このように、「つくる会」教科書には歴史を動かしてきた主体である民衆の姿は登場しない。その替わりに強調されるのが、「愛国心」にあふれ、国難に際しては「私」を捨て一致団結した「国民」の物語である。 「日清戦争の勝因としては…日本人が自国のために献身する『国民』になっていたことがある」(日清戦争) 「このような困難の中、多くの国民はよく働き、よく戦った。それは戦争の勝利を願っての行動であった」(第二次大戦下の国民生活) 国家への献身・自己犠牲を美徳とする記述のオンパレードは、とても歴史の教科書とは思えない。 徴兵制の施行を説明するくだりでは、日清戦争における木口小平のエピソード(「死んでもラッパを離しませんでした」という、あれだ)を持ち出し、「江戸時代まで武勲とは縁のなかった平民に新しい時代が訪れた」と評価する始末。お国のために命を捧げられるようになったのは、「平民」にとって感謝すべきこと、というわけだ。 事実、「つくる会」教科書は「教育勅語」を全文掲載し、「非常時には国のために尽くす姿勢、近代国家の国民としての心得を説いた教え」で、「近代日本人の人格の背骨をなすものとなった」と誉め讃えている。 ちなみに、教育基本法に関しては制定の事実を一行で伝えているだけ。「個人の尊厳を重んじ」(前文)としている教育基本法の内容には触れたくないらしい。 沖縄戦も歪曲国民の戦争協力を美化する「つくる会」教科書にかかると、「軍隊は住民を守る存在ではない」ことを物語る歴史的事実である沖縄戦も「殉国美談」にされてしまう。 「沖縄では、鉄血勤皇隊の少年やひめゆり部隊の少女たちまでが勇敢に戦って、一般住民約9万4000人が命を失い、10万人近い兵士が戦死した」 これが「つくる会」教科書の沖縄戦記述のすべてである。 兵隊の看護に動員された女子学生が「勇敢に戦って」とあるのは大ウソだ(「ひめゆり部隊」という名称からしておかしい)。一般住民の死亡が正規兵を上回ったという、沖縄戦を語る上で欠かせない事実もねじ曲げている。 何より、日本兵による住民迫害の数々(避難壕からの追い出し、食糧強奪、「自決」の強要、そして住民虐殺)には一切触れていない。 日本軍がアジア諸国で行った戦争犯罪を無視する「つくる会」教科書は、軍隊が自国民に銃口を向けた事実も隠ぺいする。すべては、戦争を美化・肯定し、「自国のために献身する」精神を子どもたちに植えつけるためだ。 「命こそ宝」が沖縄の心とすれば、「つくる会」教科書はそれと正反対の思想からできている。まさに、子どもを戦争にいざなう書というほかない。 (M) |