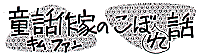| |||
カササギとカラスは永遠のライバルだ。韓国の七夕伝説では力を合わせて「烏鵲(オジャク)橋」をかける両者だが、「休戦」はその日限り。それ以外は、生き残りをかけたせめぎあいを日夜くりひろげている。 日本では、カササギは九州の一部にしか生息していない。しかし朝鮮半島では、どこにでもいるごくありふれた鳥だ。けれども、元来、済州島にはカササギは生息していなかった。 韓国なのにカササギがいないのはおかしい。人々が生態学などまだ知らなかった1963年、カササギは済州島で放鳥された。が、そのときは定住せず、70年には姿を消した。ところが89年、航空会社と新聞社の協賛で、またもや「カササギを送る運動」が実施されてしまうのである。全国から集められた46羽のカササギが3回にわけて放鳥されると、今度は済州島にしっかりと定着。2002年には、なんと、1万2千羽にまで増えたのであった。 済州島のからっ風を克服したカササギは、柿、ミカン、キャベツなどの農作物に多大な被害を及ぼすようになる。事態を重く見た済州島は、95年から巣を撤去、99年からは有害鳥獣に指定して捕獲をはじめた。それでも彼らを一掃することができず、昨年の調査でも3114羽の生息が確認されている。 ところで、韓国の鳥類学者が不思議でたまらないのが、日本のカササギだ。元々カササギは、日本にいない鳥だった。彼らがやってくるきっかけは豊臣秀吉の朝鮮侵略。出兵した佐賀藩祖の鍋島直茂が朝鮮半島から日本に持ち帰ったものが繁殖し、今日に至っているといわれている。カササギが「カチカチ」と鳴くので、「勝ち」につながるので縁起が良いとされ、「かちがらす」と呼ばれた。現在、佐賀平野と筑後平野一帯はカササギ生息地として国の天然記念物に指定されている。 さて、学者たちの質問だ。 日本のカササギは、どうして今日まで九州の一部だけに留まり、勢力を拡張させないのか? いわれてみれば確かに不思議だ。カササギは賢くて雑食性ゆえに大陸では広く分布し、圧倒的な強さを誇っている。韓国ではカラスの影が薄いほど、わが者顔で暮らしているのに、どうして日本では一部の地域だけでしか生息しないのだろうか? 日本の学者の意見は、カラスが天敵となっていて、それで勢力を拡大できずにいるとのこと。 事実、近年になって貨物船に乗ってくるなどして韓国から日本にカササギがやってきて繁殖している例も報告されているが、カラスに定着の「目」を摘み取られているようだ。 済州島にはカラスがたくさんいるのになぁ…。どうやら過去の撃退で慢心し、「スキ」を見せてしまったようだ。 |